こんにちは、しゅうく(@syuukuETF)です。
「アート(芸術)は毎日がキツイ・ツライ人にこそ必要」という記事の続編です。
今回は「映画編」
映画もなくてはならないものです。
音楽同様、現実世界と自分をきちんとリンクさせるために、映画にも定期的に触れておかないとダメになってしまいます。
なに言ってるか全然わからない
アートは生きていくうえで必要
管理人が、なぜアート(芸術)が必要と感じたか?
以下の記事にその根拠を書き綴っています。


なにによって「癒されるか」は、人によって違いますよね。
アート(芸術)に触れることによって、管理人は「癒し」を得ています。
映画編
マノエル・ド・オリヴェイラ「クレーヴの奥方」
一番好きな映画監督は、ポルトガルのマノエル・ド・オリヴェイラ(Manoel de Oliveira)です。
サブスクにもほとんどないしDVDの流通も少なく価格も高いしで、全作品は観れてません。
観た中では「クレーヴの奥方」がダントツでした。
1つ1つの画面が完璧で、徹頭徹尾その完璧さが漲った作品です。
完璧すぎるということは、「見ると疲れるんじゃないか?」と思われるかもしれませんが、全く逆で、観終わると全身から疲労が抜けていることに気付きます。
ハイ・インテンシティなものは、むしろ癒しになるという好例です。
「クレーヴの奥方」を観て以降、映画への接し方が180度変わったぐらい、今でも基準となっている作品です。
パトリック・ボカノウスキー「天使」
高校生の頃、12月24日(クリスマス・イヴ!)の一日のみ公開ということで、思い切って当時好きだった女の子を誘ってみました。
お誘いは見事撃沈、当日は1人で観に行きました。
全編がコラージュのような作品で、「ミルクが入った壺がテーブルから落ちる」など意味のないシーンを何度も繰り返したり、忙しそうだけど同じことを繰り返してるだけに見える図書館員達だったり、階段を昇ってる人達の静止画で光だけを動かしたり。
「スティーヴ・ライヒのMV」「カフカの小説の実写化」があればこんな風になるのではないか、
はたまた夢をそのまま映像化したらこんな感じなるのではないか?といったわけのわからなさが最高に心地いい映画です。
現に観に行った際も、心地良過ぎて半分寝てました。
そして観終わって、「1人で来てよかった」と心から思いました。
デートには全く向いてません。
当時とても影響を受け、「とにかくフィルムを回して撮った映像をランダムにくっつける(セリフや音楽は後付け)」映画を自分でも撮ったぐらいです(未完成で終わりましたが)
デレク・ジャーマン「The Angelic Conversation」
「わけがわからない」ついでにもう1つご紹介。
あまりよく覚えてはないのですが、全編スローモーションで、最後のほう10分ぐらいいきなり2倍速ぐらいになる、「NEU!か!」とツッコミたくなるようなんだったような気がします(間違えてたらすみません)
「天使」同様ストーリーなど全くないので、観てリラックスできないとも言えない作品です。
ジム・ジャームッシュ「Stranger Than Paradise」
この作品を観るまで、「映画というものは起承転結があるものだ」という固定観念がありました。
なので、「作品が終わったのに終わってない感」がする映画を観たのは、この「Stranger Than Paradise」が初だったかもしれません。
3人の若者が過ごす10日間を、ただただ映しただけ。
でも映画の中に流れる空気がとても心地良い。
35年ぐらい前に映画館に行った1回きりしか観てないのに、いまだに忘れられない作品です。
観終わって一週間ぐらい、主演のジョン・ルーリーの口元の真似が抜けませんでした。
ジム・ジャームッシュ「PETERSON」
愛すべき映画。
時間が穏やかに流れていて、「ただ愛する人と暮らすことの幸福」が、切り取られた映画という時間軸の過去、そして未来にも続いてるんだろうなと想像させます。
この予告編を観るだけでも、ちょっと泣いてしまいそうです。
森田芳光「メイン・テーマ」
最後はかなり個人的な作品をご紹介。
中学生の頃、多分薬師丸ひろ子が歌う主題歌が好きで、テレビで放映されると知って観たんだと思います。
当時はビデオデッキなんてなかったので、ラジカセで最初から最後までテレビから出る音声を録音し、繰り返し聴き返しました。
あまりにも繰り返し聴き過ぎて、セリフを全部覚えてしまい、シナリオを画像付きで文庫化した「カドカワフィルムストーリー」という本のセリフの間違いを赤ペンで訂正してたほどです。
当時はCDすら出てなかったので、盤面がグリーンのサントラのレコード盤を、レコードプライヤーを持ってないのに買ったりもしました。
作品としてすごく優れているわけでもないのにこれだけハマってしまったのは、やはり「時間の流れ方」なのかなと思います。
財津和夫、渡辺真知子、太田裕美、戸川純といった歌手に役者をやらせ、桃井かおりに歌手役をやらせるという逆転の発想も面白いですし、この作品がデビューの野村宏伸のあまりにヘタな演技も、肩の力を抜いて観ることが可能になってる要因なのかなと思います。
そういった「自由な感じ」が、旅する出演者達の雰囲気にも纏っていて、主演の薬師丸ひろ子のいい意味で緊張感が抜けた演技につながってる気がします。
アートは続くよどこまでも
「映画」も「音楽」同様、管理人の生活に欠かせないものです。
記事を書きながら気付いたのですが、どちらもエンターテインメントとして楽しむというより、自分が持っている特性を伸ばすもの、または欠けているピースを埋めるものとして作用しているような気がします。
「音楽」にとっての『歌詞』、映画にとっての『ストーリー』は、それほど重要視してません。
そのためか人と「音楽」や「映画」の話をしても噛みあわないことが多いのですが、そもそもそういうことは求めてなく、「自分にとって必要なもの」として、しがみつくように接しているという傾向が強いです。
でもだからといって「誰とも共有したくない」と思っているわけではなく、共有できる人がいれば思いっきり共有したいです。
アート(芸術)って、元々そのために存在するんだと思いませんか?
よろしければTwitterのフォローもお願いします!


CFD GMOコイン iDeCo QQQ TQQQ つみたてNISA インヴァスト証券 イーロン・マスク セミリタイア デリバティブ ナスダック ナスダック100 ビットコイン マネーショート マネーリテラシー レバレッジ取引 不労所得 仮想通貨 全米株式 口コミ 感想 投資 暗号通貨 楽天経済圏 自動売買 裁量トレード 見てみた 資産形成 資産運用 金融株トリプル



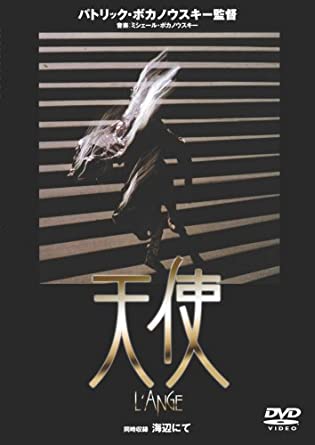


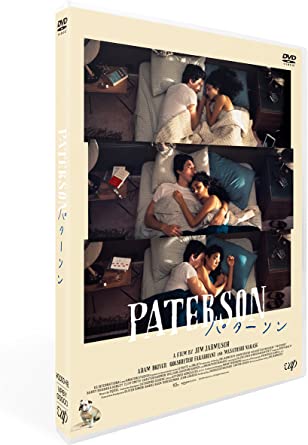
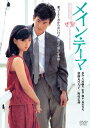

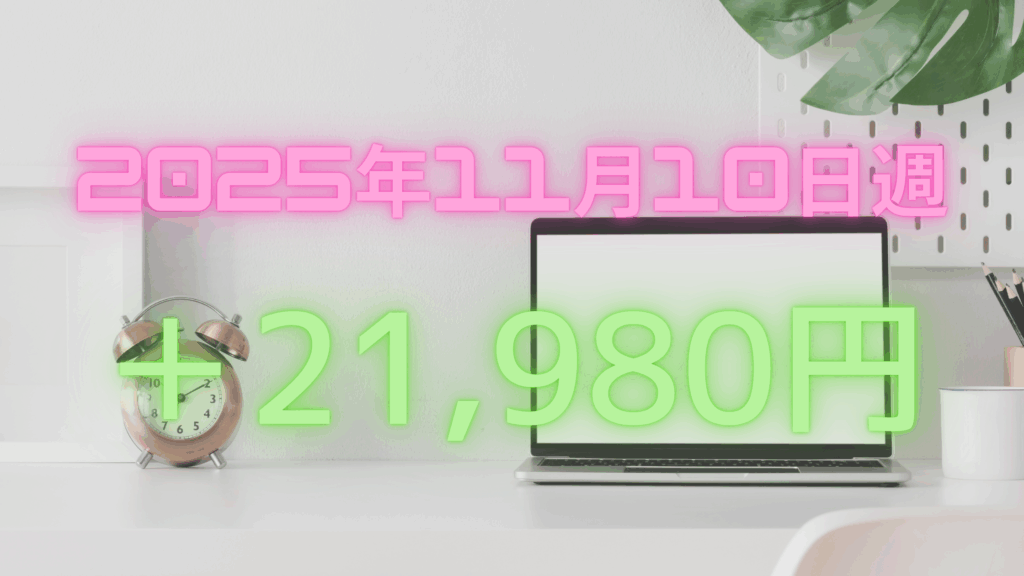
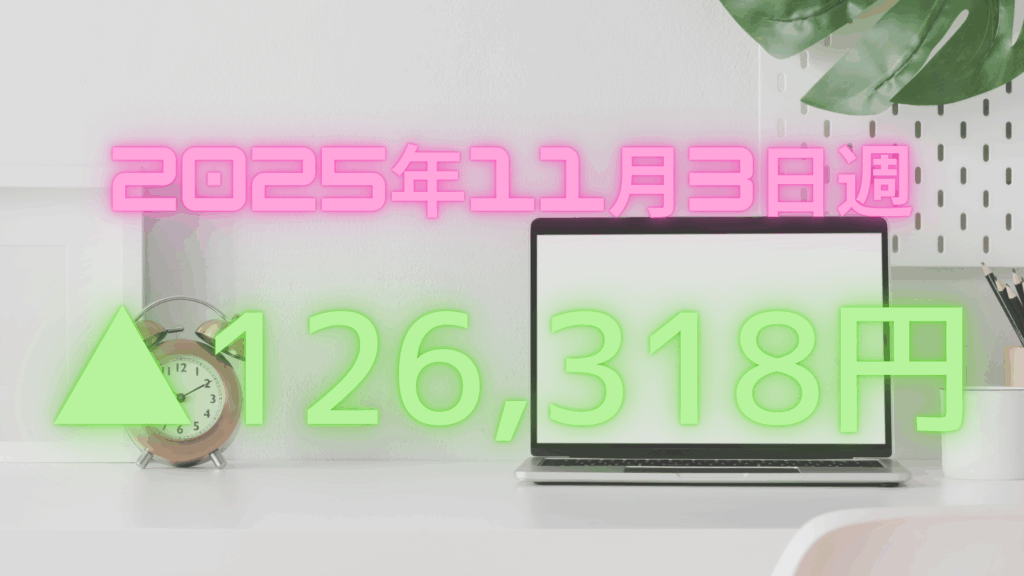
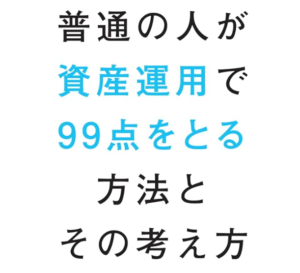





コメント